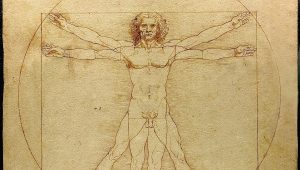親の命と子の命
親子が乗った小船が難破した。船に装備された救命胴着は一人分のみ。救命胴着を着用すれば助かるが、それなしに海に放り出されれば確実に死ぬ。救命胴着には親と子の両方を支える浮力はない。さて、この場合、親と子のどちらを助けるべきか——。
お盆だったかお正月だったか、親戚が集まった折、年上の従兄弟が教えてくれたクイズである。私より一回り以上年上の彼は、ちょっとひねったクイズや手品で年下の私たちを喜ばせるのが得意だった。
首をひねる私に彼が与えた正解は、
「親を優先すべき」。
「どうしてかというとね、親は子どもを産めるけれど、子どもは親を産めないだろ。だから、親を助けるべきなのさ。」
ニヤニヤ笑った訳知り顔の従兄弟を見上げ、ふーん、と、半ば納得しつつも、なんとなくだまされたような、どこかにウソがあるような気分で頷いた私は当時11歳くらいだったと思う。
船が難破した時には子どもから救命ボートに乗せてもらえるはずだ。子どもの命を救うために、親は自分の命を投げ出すことも厭わないはずだ、と、特に深く考えたわけではなかったが、漠然とそう信じていた当時の私には、親の命が子の命に優先するというこのクイズの答えはかなりショックなものだった。
だからだろうか、今でも飛行機に乗るとよくこの時のことを思い出す。離陸前に説明される緊急時の機材の使用方法。救命ジャケットの着用方法や酸素マスクの使い方など、儀式のように流されるビデオスクリーンに注意を払う人はほとんどいないが、酸素マスクの説明の段になると私は密かに緊張してしまう。
一昔前はこんなアナウンスが流されていた。「小さなお子さま連れのお客様は、必ず親御さんから先にマスクを装着してください」と。まず親が自分の酸素を確保した上で、子どものマスクを装着してやる。子どもを救うために親がしっかりしてなくてはいけない。その意味で親の福利は子のそれに優先される。
これがもし、酸素マスクが親子に一本ずつしかなかったとしたら。
空気が薄くなった飛行機の機内でマスクを装着すべきなのは、親なのか、子なのか・・・
もし私がもう少し頭の良い子どもだったら、「親を優先すべき」というイトコの「答え」に対し、ちょっと待ってよと議論をふっかけたかもしれない。子どもだって大きくなれば次の子どもを産むわ。親は子どもより年をとっているから早く死ぬじゃない。未来を生きる子どもの方を優先すべきだと思わない?
このように、「難破船クイズ」はある種の頭の体操として、あるいは酒の席での世間話としてはおもしろいクイズだが、本当のところ、「親は子を産めるのだから、親の命は子の命に優先する」という答えから強い不快感を覚えることは事実である。納得しつつもどこかにウソがある、というよりも、もっと深く感情のヒダを微妙に逆撫でされるような不快感。
その理由の一つには、このクイズが「悲しみ」や「罪悪感」といった感情をまったく無視していることにある。親を亡くした子の悲しみと子を亡くした親の悲しみ。親を犠牲にして生き延びた罪悪感と、子を犠牲にして生き延びた罪悪感。これのどちらが重いのか、もちろん較べる術がないのだが、先のクイズの答えが導く命題は、これらの点を考慮の外に置き去りにする。
さらに、「親は子が産めるが故に、子どもが犠牲なるべきだ」とする命題は「親が産む子どもはどれも代替可能である」ということを前提としている。つまり、船の難破から生還した親が新たに産む子どもは、犠牲になった子どもと取り替え可能、すなわち代替可能だと言っている。
たとえば不慮の事故や病気で子どもを亡くした親に対して「また産めばいいじゃないの」という言葉が、いかに慰めの言葉として不適切か、悲しみの中にある人をいかに傷つけるものか、いかに無神経な言葉なのかと考えればわかりやすい。
世代としての「子ども」、あるいはカテゴリーとしての「子ども」は、確かに実存する。そして、そのレベルにおいて我々は子どもの「量」と「質」について議論することができる。しかし、一人の親にとって、船の遭難で亡くした「あの子」と、その後で生まれた「この子」はまったく異なる存在なのである。「あの子」を失った悲しみは永遠に癒えることはなく、「あの子」を失ってできた心の穴は誰にも埋めることはできない。「あの子」がどんな子だったにせよ—もしかしたらとんでもない放蕩息子だったかもしれないが—その子の代わりは誰にもできないのである。
そんな「とりかえのきかない命」を、私たちは神から授かった。
にもかかわらず、海に投げ出されても救命胴着を一着分しか与えられない親子、飛行機の機内の空気が薄くなっても酸素マスクが一セットしかもらえない親子が、私たちが生きる社会にはたくさん存在する。そのことを私たちは絶対に忘れてはならない。
たとえば、という”数字”をあげれば、児童虐待が原因で命を落とす子どもは年間100人近く。一週間に一人か二人の計算だ。この半数近くが心中によるものだ。親自身が追い詰められて死を選び、その過程で道連れにされた子どもたち。一つ一つの事例は胸がつぶれるほど痛ましく、難破船のクイズどころの話じゃない。海に投げ出されて救いを探し求めたはずの彼らに、どんな救いの手がのべられたのか。彼らに救命胴着一着も与えられなかったことを、私たちは肝に銘じるべきである。
未来の社会を担う子どもを育てる親を支援すること。
私たちに課せられた大きな課題である。
『家庭の友』2013年12月号 掲載